
こんにちは。行政書士の落合です。
不動産業界に参入しようと考えている皆さん、あるいは事業拡大を検討している企業様、宅地建物取引業(宅建業)の許可は、その第一歩として不可欠なものです。しかし、「許可申請って難しそう」「どんな書類が必要なの?」と、その手続きの複雑さに戸惑っている方も少なくないでしょう。
宅建業の許可は、単に書類を揃えれば良いというものではありません。法律で定められた厳しい要件を満たし、その後の適正な事業運営が求められます。
この記事では、宅建業許可の基本から、申請手続きの具体的な流れ、そして許可取得後の維持管理のポイントまで、行政書士の視点から詳しく解説します。
目次
1| 宅建業許可とは?なぜ必要?
・許可の区分:大臣許可と知事許可
- 人的要件(宅地建物取引士の設置)
- 事務所の要件
- 財産的要件(お金の要件)
- 欠格要件に該当しないこと
- 申請者情報と履歴の透明性
・申請の流れ(一般的な例)
・必要書類の例(一部)
- 5年ごとの「更新申請」を忘れずに
- 変更があった場合の「変更届」を速やかに提出
- 宅地建物取引士の継続的な配置
- 営業保証金または保証協会への加入継続
- 法令遵守(コンプライアンス)の徹底
5| まとめ ~不動産ビジネスの要「宅建業許可」の取得・維持は行政書士へ~
1| 宅建業許可とは?なぜ必要?

宅地建物取引業とは、「宅地」または「建物」の売買・交換・賃貸の代理・媒介を、反復継続して行う事業のことです。具体的には、不動産の売買仲介、賃貸仲介、建売住宅の販売、マンション分譲などがこれに該当します。
これらの事業を営むためには、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可(免許)を取得することが義務付けられています。無許可で宅建業を営むことは違法行為であり、罰則の対象となります。
許可の区分:大臣許可と知事許可
宅建業の許可には、事業所の所在地によって以下の2種類があります。
-
知事許可(〇〇県知事免許)
一つの都道府県内のみに宅建業の事務所(本店・支店)を設置して事業を営む場合に必要な許可です。例えば、東京都内にのみ事務所がある場合は、東京都知事の許可を受けます。 -
大臣許可(国土交通大臣免許)
二つ以上の都道府県にわたって宅建業の事務所を設置して事業を営む場合に必要な許可です。例えば、東京都と神奈川県の両方に事務所を設置する場合は、国土交通大臣の許可を受けます。
どちらの許可が必要かは、事務所の設置状況によって決まります。申請先が異なるため、自社に必要な許可を正確に把握することが重要です。
2| 宅建業許可取得の重要要件:5つのポイント

宅建業の許可を取得するためには、宅地建物取引業法で定められた以下の要件をクリアする必要があります。これらは「人」「場所」「お金」「資格」に関する厳しい基準であり、一つでも欠けていると許可は得られません。
1.人的要件(宅地建物取引士の設置)
宅建業を営む事務所には、専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
-
設置基準: 事務所ごとに、業務に従事する者(常勤役員や従業員など)5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置く必要があります。
-
「専任」とは: その事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事していることを指します。他社の役員や他の宅建業者の従業員と兼任することはできません。
-
資格登録: 宅地建物取引士の資格登録が完了していることが必須です。
2.事務所の要件
宅建業を営む事務所は、その事業を継続的に行うに足る独立した形態を備えている必要があります。
-
独立性: 他の会社や個人の住居と明確に区別され、宅建業専用のスペースとして独立していることが求められます。例えば、自宅の一部を事務所とする場合でも、パーテーションなどで明確に区切られ、専用の出入り口があるなど独立性が確保されている必要があります。
-
継続性: 事業活動を安定して行える場所であることが求められます。テント張りの仮設店舗や他社の片隅を借りただけの場所は認められません。
3. 財産的要件(お金の要件)
宅建業は顧客から高額な金銭を預かるなど、大きな責任を伴う事業であるため、一定の財産的基礎が求められます。
-
自己資金の確保
法人:直前1年間の貸借対照表において、純資産の額が一定以上であることが必要です。
個人事業主: 自己資金(預貯金など)が一定以上であることが必要です。
- 営業保証金の供託または保証協会への加入
顧客との取引で生じる損害に備えるため、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会(ハトマークやラビットマークなど)に加入する必要があります。 -
営業保証金
主たる事務所に1,000万円、その他の事務所1か所につき500万円を法務局に供託します。 -
保証協会への加入
営業保証金よりはるかに少額の弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、その他事務所1か所につき30万円)を納付することで、保証協会の社員となり、万が一の際の弁済業務は協会が行います。ほとんどの宅建業者が保証協会に加入します。
4.欠格要件に該当しないこと
申請者(法人であれば役員全員、個人事業主であれば本人)や、政令で定める使用人(支店長など)が、以下の欠格要件のいずれにも該当しないことが求められます。
-
過去に禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過していない者
-
宅建業法違反などで罰金刑を受け、その執行が終わってから5年を経過していない者
-
暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
-
心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者
-
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
-
過去に宅建業の免許を取り消されてから5年を経過していない者
5. 申請者情報と履歴の透明性
申請者(法人の場合は会社情報と役員全員、個人の場合は本人)の正確な情報と、過去の経歴を詳細に申告する必要があります。これは、事業者の信頼性と健全性を確認するためです。
3| 宅建業許可申請の具体的な流れと必要書類
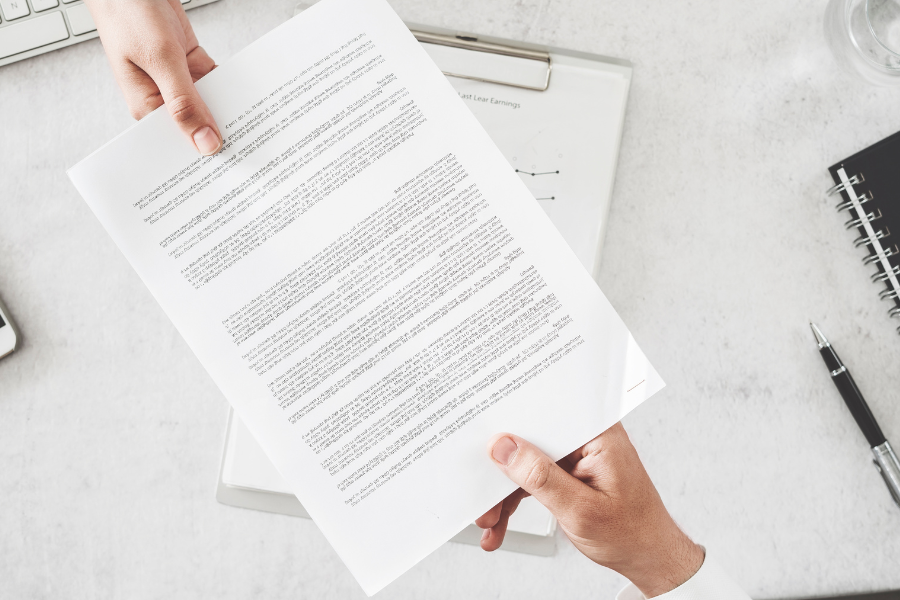
宅建業許可の申請手続きは非常に複雑で、多くの書類を正確に準備する必要があります。
申請の流れ(一般的な例)
-
事前準備・要件確認: 宅地建物取引士の確保、事務所の選定、自己資金の確認など、上記の要件を満たしているか確認します。
-
必要書類の収集・作成: 膨大な数の書類(法人の登記事項証明書、役員の住民票・身分証明書・納税証明書、宅地建物取引士証のコピー、事務所の賃貸借契約書・図面など)を収集し、申請書を作成します。
-
申請書の提出: 管轄の都道府県庁(知事許可の場合)または地方整備局(大臣許可の場合)へ申請書類を提出します。
-
審査: 行政庁による書類審査、場合によっては事務所の現地調査が行われます。
-
許可通知: 審査が問題なく完了すれば、許可通知書が郵送されます。
-
営業保証金の供託または保証協会への加入: 許可通知を受けたら、免許交付前に、営業保証金の供託(法務局)または保証協会への加入・弁済業務保証金分担金の納付が必要です。
-
営業開始: 上記が完了し、免許が交付されれば、晴れて宅建業をスタートできます。
必要書類の例(一部)
-
宅地建物取引業免許申請書
-
役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士の略歴書・誓約書
-
住民票、身分証明書、成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書
-
納税証明書
-
法人の登記事項証明書、定款
-
事務所の平面図、写真、賃貸借契約書
-
貸借対照表、損益計算書(法人の場合)
-
預金残高証明書(個人の場合)
-
宅地建物取引士証の写し、宅地建物取引士の専任を証する書面
これらの書類は、一つでも不備があると受理されず、何度も修正を求められることになります。専門家である行政書士に依頼することで、スムーズな申請が可能です。
4| 宅建業許可取得後も重要!維持管理のポイント

宅建業許可は、一度取得したら終わりではありません。許可を継続的に維持し、法に則った健全な事業運営を行うためには、以下のポイントを常に意識する必要があります。
1.5年ごとの「更新申請」を忘れずに
建設業許可と同様に、宅建業許可も有効期間は5年間です。期間満了日の90日前から30日前までに、必ず更新申請を行う必要があります。更新を怠ると、許可は失効し、新規で取り直すことになります。日々の業務に追われてうっかり忘れてしまうことがないよう、カレンダーに登録するなど、管理体制を構築しましょう。
2.変更があった場合の「変更届」を速やかに提出
許可取得後に、会社や役員、事務所、宅地建物取引士などに変更があった場合は、内容に応じて30日以内、または遅滞なく行政庁に「変更届」を提出する義務があります。
主な変更届の対象事項:
-
商号または名称、所在地(本店・支店)
-
役員(氏名、住所、役職など)、政令で定める使用人
-
専任の宅地建物取引士の変更、退職、氏名変更など
-
資本金の額
-
保証協会加入の有無、主たる事務所の名称・所在地
-
従業者数の変更
-
その他、免許申請事項に変更があった場合
これらの変更届を怠ると、虚偽の申請とみなされたり、行政指導や最悪の場合には免許取り消しの対象となることもあります。特に、専任の宅地建物取引士が退職したにもかかわらず後任を補充せず、届出もしないといったケースは、許可要件を満たさない状態が続き、重大なリスクとなります。
3.宅地建物取引士の継続的な配置
常に事務所ごとに「業務に従事する者5人に1人以上」の割合で専任の宅地建物取引士を配置する義務があります。退職者が出た場合は、速やかに補充し、変更届を提出しましょう。
4.営業保証金または保証協会への加入継続
宅建業を営む限り、営業保証金を供託しているか、保証協会に加入している状態を継続しなければなりません。万が一、供託金が減額されたり、保証協会を脱退したりした場合は、速やかに対応が必要です。
5.法令遵守(コンプライアンス)の徹底
宅地建物取引業法をはじめ、民法、建築基準法、消費者契約法、個人情報保護法など、関係法令を遵守することは、宅建業を継続するための大前提です。不正行為や違反行為は、行政処分(指示処分、業務停止処分、免許取り消し処分など)に直結します。
-
重要事項説明の適切な実施
-
誇大広告の禁止
-
不当な顧客勧誘の禁止
-
帳簿の備え付け・保管
これらを徹底し、顧客からの信頼を得ることが、事業の安定的な成長に繋がります。
5| まとめ ~不動産ビジネスの要「宅建業許可」の取得・維持は行政書士へ~

宅建業許可の申請から、日々の維持管理に至るまで、その手続きは多岐にわたり、専門的な知識が求められます。日々の業務に忙しい経営者様やご担当者様にとって、これらの手続きを正確かつ迅速に進めることは大きな負担となるでしょう。
当事務所は、宅建業許可の専門家として、皆様を強力にサポートいたします。
-
複雑な申請書類の作成・提出代行
要件確認から書類作成、行政庁との折衝まで、全てお任せください。 -
許可取得後の維持管理サポート
変更届の管理、更新時期のアラート、法改正情報の提供など、継続的なサポートを提供します。 -
トラブル予防のためのアドバイス
日常業務における法務リスクを低減するための助言も行います。
「初めての申請で何から手をつけて良いか分からない」「変更届を出し忘れていないか不安」「本業に集中したい」——そうお考えでしたら、ぜひ一度、ご相談ください。貴社の事業が安心して、そして力強く発展していくよう、全力でお手伝いさせていただきます。

執筆者
行政書士おちあい事務所 行政書士 落合真美
遺言や相続、建設業や産廃業などの許可申請でサポートを提供。人に、会社に、寄り添うことを大切にしています。



