
こんにちは。行政書士の落合です。
「オフィスから出る紙くずは、普通のゴミとして捨てていいのだろうか?」「製造工程で出た廃液は、どこに頼めば正しく処理してもらえるのだろう?」
企業の総務・経理担当者様から、このようなご相談をいただくことがあります。廃棄物の処理に関する法律(廃棄物処理法)は複雑で、一つ間違えると、「不法投棄」という重大な罰則リスクを負うことになります。
特に、事業活動に伴って生じる廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の明確な区別があり、処理方法や責任が全く異なります。この違いを曖昧にしたままでは、御社のコンプライアンス体制に大きな穴が空いているのと同じです。
本コラムでは、廃棄物の正しい分類と、企業が必ず守るべき処理委託の基本ルールについて解説します。
目次
1|廃棄物の二大分類:判断の基準は「事業活動」
1-1 一般廃棄物
1-2 産業廃棄物
2| 厳格に定められた20種類の産業廃棄物
2-1 あらゆる事業活動に伴って生じる12種類
2-2 特定の事業活動に伴って生じる8種類
義務①:マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付
義務②:許可を持つ業者への委託
義務③:委託契約書の作成と保管
1| 廃棄物の二大分類:判断の基準は「事業活動」

廃棄物処理法において、ゴミは大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の二つに分けられます。この分類の最も重要な判断基準は、「事業活動に伴って排出されたかどうか」です。
1-1 一般廃棄物
家庭から出るゴミ(生ゴミ、紙くず、プラスチックなど)や、事業活動に伴って生じたゴミのうち、産業廃棄物に分類されないものを指します。具体的には、オフィスや店舗から出る紙くず、茶殻、従業員の弁当の食べ残しなどが該当します。
1-2 産業廃棄物
工場、建設現場、オフィス、店舗など、あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものを指します。
重要なのは、排出元の業種や排出された場所を問わず、法律で定められた20種類の廃棄物に該当すれば、それはすべて産業廃棄物として扱われるということです。
例えば、飲食店から出る生ゴミは「事業系一般廃棄物」ですが、建設現場から出る木くずは「産業廃棄物」になります。この分類の混同が、法的な問題を引き起こす主な原因となっています。
2|厳格に定められた20種類の産業廃棄物

法律で定められた産業廃棄物の20種類は、その性質から「あらゆる事業活動に伴って生じるもの」と「特定の事業活動に伴って生じるもの」の2つに大別されます。
2-1 あらゆる事業活動に伴って生じる12種類
これらの12種類は、業種を問わず、全ての事業活動で発生すれば産業廃棄物となります。
-
燃え殻
-
汚泥(産業排水処理後の泥など)
-
廃油
-
廃酸
-
廃アルカリ
-
廃プラスチック類(あらゆる産業から排出されるプラスチック製品のくず)
-
ゴムくず
-
金属くず
-
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
-
鉱さい
-
がれき類
-
ばいじん(集じん装置で集められたもの)
2-2 特定の事業活動に伴って生じる8種類
これらの8種類は、特定の業種(建設業、製造業、電気・ガス・水道業など)の事業活動から排出された場合に限り、産業廃棄物となります。
-
紙くず(建設業など特定の業種)
-
木くず(建設業など特定の業種)
-
繊維くず(建設業など特定の業種)
-
動植物性残さ(食料品製造業など)
-
動物系固形不要物
-
動物のふん尿
-
動物の死体
-
以上の廃棄物を処分するために処理したもの(例:コンクリート固形化物など)
この20種類に加え、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を与える恐れのあるものは「特別管理産業廃棄物」に指定されており、さらに厳格な処理基準が求められます。
御社の事業内容から、どのような廃棄物が出るかを正確に把握し、リストと照らし合わせることが、コンプライアンスの第一歩となります。
3|排出事業者が負うべき「最終責任」と処理委託の基本ルール
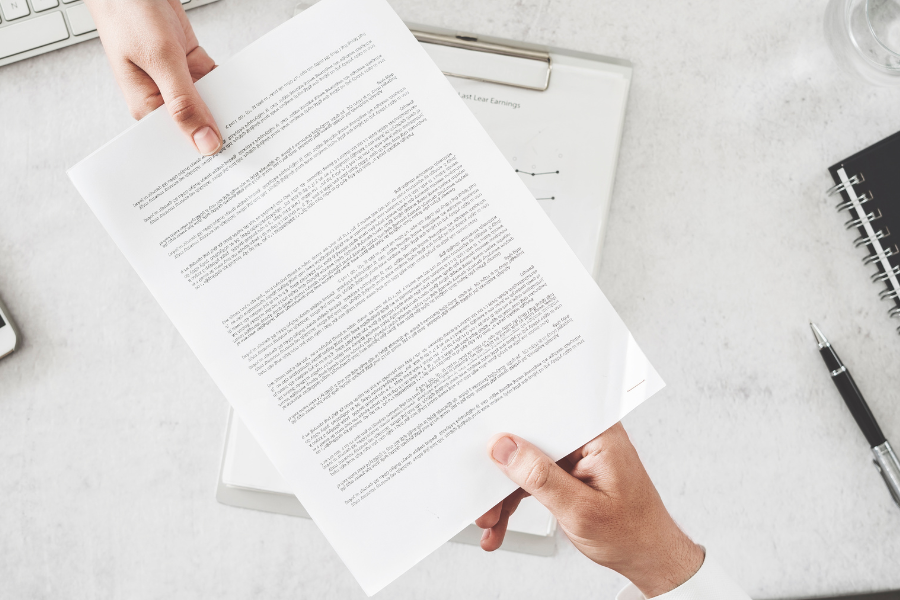
産業廃棄物の処理は、排出事業者(ゴミを出した企業)に全責任があります。これが「排出事業者責任」の原則です。
義務①:マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付
処理を外部の業者に委託する場合、排出事業者は「マニフェスト」と呼ばれる管理票を交付する義務があります。
-
目的
廃棄物が収集、運搬、中間処理、最終処分に至るまでの全過程を追跡し、「どこへ、誰が、どのように処理したか」を確認するためのものです。 -
義務
交付したマニフェストは、最終処分が完了した後、5年間保管しなければなりません。マニフェストがない状態で委託したり、不実の記載をしたりすると罰則の対象になります。
義務②:許可を持つ業者への委託
産業廃棄物の収集運搬や処分は、都道府県知事などから必要な許可を得ている業者にしか委託できません。
-
注意点
委託する前には、必ず業者の「許可証」を確認し、委託したい廃棄物の種類や処理方法が、業者の許可範囲に含まれているかをチェックする必要があります。もし、無許可業者や許可範囲外の業者に委託した場合、排出事業者も連帯責任を問われます。
義務③:委託契約書の作成と保管
処理を委託する際には、必ず書面で契約を締結し、契約書を5年間保管しなければなりません。この契約書には、廃棄物の種類や数量、処理の方法など、法定の事項をすべて記載する必要があります。
4|まとめ ~安心のコンプライアンスを~

産業廃棄物の処理は、単にコストの問題ではなく、企業存続に関わるコンプライアンス(法令遵守)の問題です。
-
「排出する廃棄物の種類が本当に20種類に該当するのか?」
-
「委託先の業者が適切な許可を持っているか?」
-
「マニフェストの運用方法に間違いはないか?」
これらの複雑な判断と煩雑な書類作成を、本業の傍らで行うのは非常に大きな負担となります。
私たち行政書士は、専門家として、御社の事業内容を正確に把握し、廃棄物の分類から、適正な処理委託契約、マニフェストの運用指導までを一貫してサポートします。
専門家に依頼することで、不法投棄による社会的な信用失墜や、数百万単位の罰則リスクから御社を守ることができます。御社の廃棄物処理に少しでも不安を感じられたら、ぜひ一度ご相談ください。
ここまでお読み下さりありがとうございます。

執筆者
行政書士おちあい事務所 行政書士 落合真美
遺言や相続、建設業や産廃業などの許可申請でサポートを提供。人に、会社に、寄り添うことを大切にしています。



