
こんにちは。行政書士の落合です。
大切なご家族のために遺言書を作成しようと考えている方、あるいは、遺言書が見つかったけれど、何から手をつけて良いか分からないと悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。遺言書は故人の最後の意思表示であり、その想いを実現するための大切なツールです。しかし、「遺言書があるからもう安心」と考えるのは、実は少し早計かもしれません。遺言書があっても、それが確実に実行されるためには、「遺言執行者」の存在が非常に重要になります。
遺言執行者とは一体どんな役割を担い、なぜその存在が必要なのでしょうか? このコラムでは、遺言執行者の基本から、その具体的な職務、選任方法、そして行政書士がどのようにサポートできるのかについて、行政書士の視点から詳しく解説します。
目次
1| 遺言執行者とは?その重要性と必要性
1-1 遺言執行者の定義
1-2 なぜ遺言執行者が必要なのか?
2| 遺言執行者になれる人・なれない人
2-1 遺言執行者になれる人
2-2 遺言執行者になれない人
3| 遺言執行者の選任方法
3-1 遺言書で指定する
3-2 家庭裁判所に選任を申し立てる
3-3 遺言書で第三者に選任を委託する
4| 遺言執行者の具体的な職務と手続き
4-1 相続人への就任通知
4-2 相続財産の調査・目録作成
4-3 相続財産の管理・処分
4-4 遺贈の実行
4-5 遺言執行完了の報告
4-6 その他の職務(必要に応じて)
5| 遺言執行を行政書士に依頼するメリット
5-1 法務の専門知識と経験
5-2 中立的な立場での対応
5-3 相続人の負担軽減
5-4 トラブルの未然防止
5-5 ワンストップでのサポート(他士業連携)
1| 遺言執行者とは?その重要性と必要性

1-1 遺言執行者の定義
遺言執行者とは、文字通り、故人が遺した遺言書の内容を、その意図通りに実現するための手続きを行う人(または法人)のことです。遺言書に書かれた内容は、故人の最後の願いです。しかし、遺言書があるだけでは、財産が自動的に相続人のものになったり、遺贈が実行されたりするわけではありません。多くの場合、名義変更や各種手続きが必要となります。
遺言執行者は、これらの手続きを、相続人全員の協力なしに、遺言者の代理人として単独で行う強力な権限を持っています。
1-2 なぜ遺言執行者が必要なのか?
「遺言書があれば、相続人が勝手に手続きしてくれるのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、遺言執行者の存在は、以下のような点で非常に重要です。
-
遺言内容の確実な実現
遺言者が残した「この財産を〇〇に渡したい」「△△団体に寄付したい」といった具体的な指示を、滞りなく実行します。遺言執行者がいなければ、相続人同士の話し合いが必要となり、意見の相違から遺言内容が実現されないリスクがあります。 -
相続人間のトラブル防止
遺言執行者がいれば、相続人同士で財産分与を巡る直接的な交渉をする必要がなくなるため、感情的な対立を避け、円満な相続を促すことができます。遺言執行者は中立的な立場で手続きを進めます。 -
複雑な手続きの代行
不動産の名義変更(登記)、預貯金の解約・払い出し、有価証券の移管など、相続手続きは非常に専門的で煩雑です。遺言執行者がこれらの手続きを代行することで、相続人の負担を大幅に軽減できます。 -
遺言の効力確保
例えば、認知している子を相続人にする「認知」や、相続人の廃除(相続権を失わせること)などは、遺言執行者がいないと法的な手続きを進めることができません。
2| 遺言執行者になれる人・なれない人

2-1 遺言執行者になれる人
-
相続人
遺言によって財産を受け取る相続人自身も、遺言執行者になることができます。 -
相続人以外の人
親族(配偶者、子、兄弟姉妹など)、友人、知人。 -
専門家
弁護士、司法書士、行政書士、税理士など。 - 法人
信託銀行や一部の弁護士法人、司法書士法人なども遺言執行者となることができます。
2-2 遺言執行者になれない人
-
未成年者
法律行為を単独で行えないため。 -
破産者
財産管理能力が認められないため。 -
欠格事由がある者
過去に不正行為などで相続に関して法的な問題を起こした者など。
遺言執行者は、遺言者の死後にその意思を尊重し、公平かつ確実に手続きを進める責任があります。そのため、相続人ではない中立的な立場の人や、法務の専門家を選任することが、トラブルなく手続きを終えるための賢明な選択と言えます。
3| 遺言執行者の選任方法
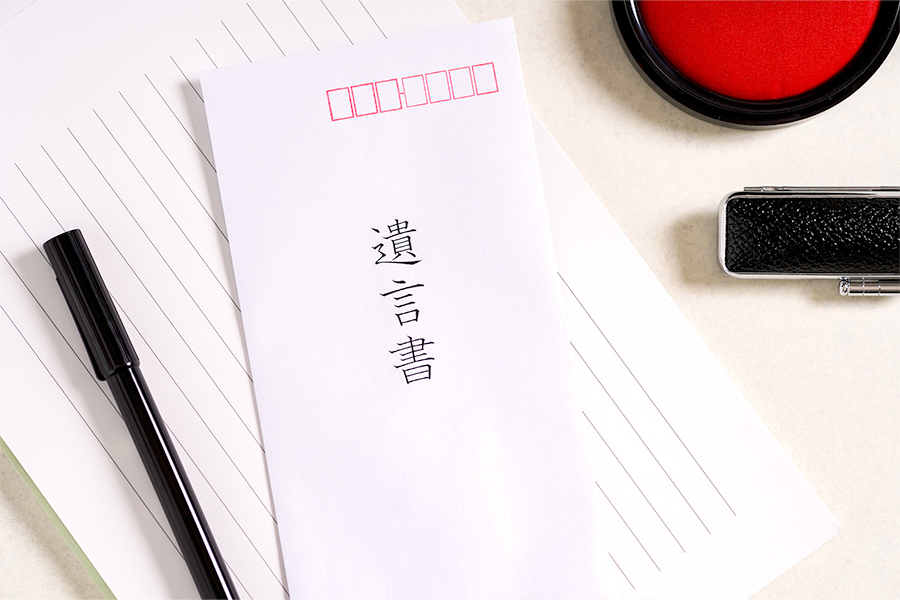
3-1 遺言書で指定する
最も一般的で推奨される方法です。遺言書の中に、「遺言執行者として〇〇(氏名)を指定する」と明確に記載します。
-
メリット
遺言者の意思が直接反映されるため、最もスムーズです。相続人同士での選任協議が不要となり、死後の手続きが迅速に進みます。 -
注意点
遺言執行者に指定された人が、その役割を引き受ける意思があるか(就職の意思)を確認しておくことが重要です。また、指定された人が遺言者より先に亡くなったり、病気などで職務を遂行できなくなったりした場合に備え、予備の執行者を指定しておくか、「遺言執行者がいない場合は、家庭裁判所に選任を申し立てる」旨を記載することも検討しましょう。
3-2 家庭裁判所に選任を申し立てる
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された遺言執行者が就職を拒否したり、既に亡くなっていたりする場合などには、利害関係人(相続人、受遺者、債権者など)が家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任を申し立てることができます。
-
メリット
家庭裁判所が中立的な立場から適切な人物を選任してくれるため、公平性が保たれやすいです。 -
デメリット
家庭裁判所での手続きに時間と費用がかかります。裁判所が選任する遺言執行者は、弁護士や司法書士といった専門家になることが多く、その報酬も発生します。
3-3 遺言書で第三者に選任を委託する
遺言書の中で、「〇〇に遺言執行者の選任を委託する」と記載し、特定の第三者(例えば、信頼できる親族や顧問弁護士など)に選任を任せる方法です。
-
メリット
遺言者が直接選任する必要がなく、柔軟性があります。 -
デメリット
委託された人が必ずしも適任者を選んでくれるとは限らないリスクもあります。
4| 遺言執行者の具体的な職務と手続き

遺言執行者の職務は多岐にわたりますが、主なものは以下の通りです。
4-1 相続人への就任通知
遺言執行者に就任したら、まずは速やかに相続人全員に対し、遺言執行者になった旨と、遺言の内容を通知します。これにより、相続人は遺言執行者の存在を認識し、手続きの透明性が保たれます。
4-2 相続財産の調査・目録作成
故人のプラスの財産(不動産、預貯金、有価証券など)とマイナスの財産(借金、未払い金など)を正確に調査し、相続財産目録を作成します。この目録は、今後の手続きの基本となります。
4-3 相続財産の管理・処分
遺言内容に基づいて、不動産の名義変更登記手続き、預貯金口座の解約・払い出し、有価証券の移管手続きなどを行います。遺言執行者は、これらの手続きを相続人の同意なしに単独で行う権限を持ちます。
4-4 遺贈の実行
特定の財産を相続人以外の人(受遺者)に遺贈する旨の記載があれば、その内容に従って受遺者への財産の引き渡しや名義変更を行います。
4-5 遺言執行完了の報告
全ての職務が完了したら、相続人に対し、その旨と財産処理の経緯を詳細に報告します。
4-6 その他の職務(必要に応じて)
-
認知手続き
遺言で子を認知する旨が記載されていれば、遺言執行者が役所に認知届を提出します。 -
相続人の廃除・取り消し
遺言で相続人の廃除またはその取り消しをする旨が記載されていれば、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。 -
遺言執行費用や報酬の精算
遺言執行に要した費用を相続財産から精算し、遺言に報酬の記載があれば、その報酬を受け取ります。
5| 遺言執行を行政書士に依頼するメリット

遺言執行者は、法律知識と実務経験が求められる重要な役割です。ご自身や相続人が遺言執行者になることも可能ですが、以下のような理由から、行政書士に依頼することをおすすめします。
5-1 法務の専門知識と経験
行政書士は、相続に関する法知識(民法、相続法など)や、戸籍収集、遺産分割協議書作成、各種許認可申請などの実務経験が豊富です。複雑な遺言内容や財産構成でも、適切かつスムーズに手続きを進めることができます。
5-2 中立的な立場での対応
相続人の一人である方が遺言執行者になると、他の相続人から不公平感を持たれたり、疑念を抱かれたりするリスクがあります。行政書士は、特定の相続人に肩入れすることなく、遺言者の意思を尊重し、公平な立場で職務を遂行します。
5-3 相続人の負担軽減
相続手続きは、戸籍収集だけでも時間と手間がかかり、慣れない手続きは精神的な負担も大きいです。行政書士に任せることで、相続人は故人を偲ぶ時間に充てたり、ご自身の生活を立て直したりすることに集中できます。
5-4 トラブルの未然防止
遺言執行の過程で、相続人間の意見の相違や、法的な解釈の違いなどからトラブルに発展する可能性があります。行政書士は、専門家としての知識を活かし、事前にリスクを予測し、トラブルを未然に防ぐための助言や対応が可能です。
5-5 ワンストップでのサポート(他士業連携)
遺言執行には、不動産登記(司法書士)、相続税申告(税理士)、訴訟・調停(弁護士)など、他の士業の専門業務が必要になる場合があります。行政書士は、必要に応じてこれら他士業の専門家と連携し、窓口となってスムーズな手続きを提供できます。当事務所も、信頼できる他の士業と連携し、包括的なサポートが可能です。
6| まとめ ~故人の想いを未来へ繋ぐために~

遺言執行者は、故人が遺した「最後のメッセージ」である遺言書を、正確かつ確実に現実のものとするための重要な役割を担います。遺言書を作成する段階で遺言執行者を指定しておくこと、そして、その選任を法務の専門家である行政書士に依頼することは、遺されたご家族の負担を軽減し、相続を円満に進めるための賢明な選択です。
いかがでしたでしょうか。「誰に相談したらいいか分からない」「手続きが複雑で不安」といったお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、当所へご相談ください。故人の大切な想いを、次の世代へと確実に繋ぐお手伝いをさせていただきます。

執筆者
行政書士おちあい事務所 行政書士 落合真美
遺言や相続、建設業や産廃業などの許可申請でサポートを提供。人に、会社に、寄り添うことを大切にしています。



