
こんにちは。行政書士の落合です。
「相続」と聞くと、現在の民法で定められた「法定相続分」や「遺産分割協議」を思い浮かべる方がほとんどでしょう。しかし、日本の長い歴史の中には、まったく異なる相続の仕組みが存在していました。それが、戦前の旧民法に定められていた「家督(かとく)相続」です。
現代ではこの家督相続制度は廃止されていますが、実は今でも、この制度が関係してくるケースが少なからず存在します。特に、何代も前の相続が関係する古い不動産の登記や、家族間で「家は長男が継ぐもの」という昔ながらの考え方が根強く残っている場合に、思わぬトラブルの火種になることがあるのです。
わたくしが亡くなった方の手続きや調査を進める際、誰が相続人になるのか、財産を誰が承継するのかが現代の常識とは全く異なる結果になるという困惑が、本当に多く見られます。この「ズレ」が、古い時代の相続登記が放置された不動産などで、現代の私たちに複雑な問題として現れてくるのです。
このコラムでは、家督相続とは具体的にどのような制度だったのか、なぜ廃止されたのか、そして現代においてどのように影響してくるのかを行政書士の視点から分かりやすく解説します。
「うちの古い土地も関係あるかも?」「親が『家を継げ』と言っているけど…」と思い当たる節のある方は、ぜひご一読ください。
目次
1.家督相続の主な特徴
2.なぜ「家督相続」が必要とされたのか(歴史的背景)
1.何代も前の相続登記がなされていない不動産
~対処法~
2.「家は長男が継ぐもの」という慣習が残る場合
~対処法~
1| 家督相続とは?「家」を継ぐための旧制度
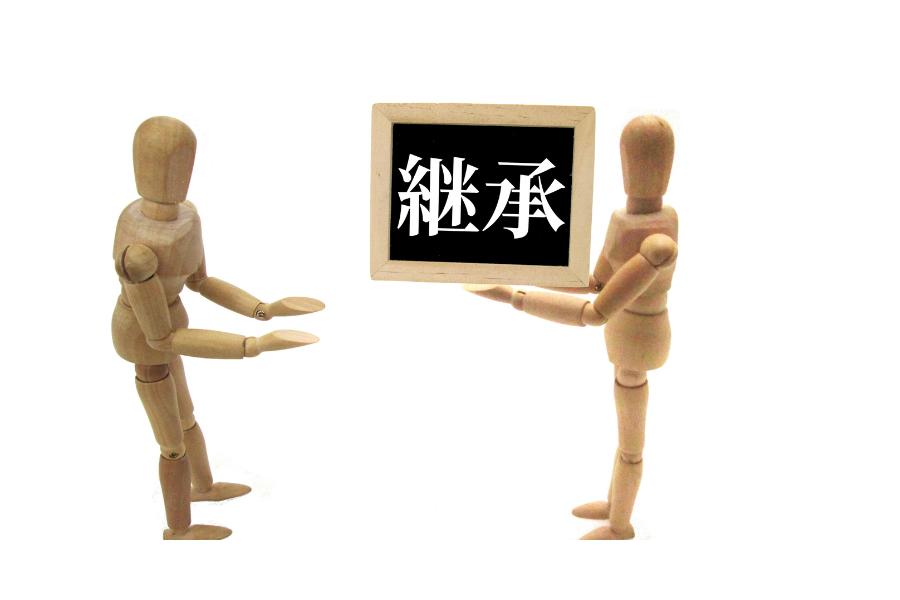
「家督相続」は、明治31年(1898年)に制定された旧民法(明治民法)において定められていた相続制度です。現代の相続が「個人」の財産を相続人が分割して承継するのに対し、家督相続は「家」という単位と、その「家長(戸主)」の地位を維持・継承することを最優先とした制度でした。
1.家督相続の主な特徴
- 「戸主」が全てを相続
家には「戸主」という家長がおり、戸主が死亡したり、隠居したり、あるいは特定の婚姻形態(入り婿など)になったりすると、家督相続が開始されました。そして、原則として「家督相続人」が戸主の地位と、それに付随する一切の権利義務(財産を含む)を包括的に単独で承継しました。 -
長男が優先
家督相続人となるのは、基本的には長男でした。長男がいない場合や、長男が家督相続人となれない場合は、他の男子(二男など)、あるいは長女、または戸主が指定した者が家督相続人となることができました。しかし、他の兄弟姉妹や配偶者には、原則として相続権が認められませんでした。これが、現代の相続との最も大きな違いです。 -
「家」の存続が目的
この制度は、家業や土地など、代々受け継がれる「家」の財産を細分化させず、特定の者に集中させることで、「家」が永続的に存続し、社会における役割を果たしていくことを目的としていました。
2.なぜ「家督相続」が必要とされたのか?(歴史的背景)
明治時代の日本は、近代国家として富国強兵を目指し、国の基盤を固める必要がありました。その中で、「家」という単位は社会の最小単位であり、その秩序と安定が国家の安定につながると考えられました。家督相続制度は、家父長制を柱とする「家制度」を法的に支えるものであり、一家の財産を長子に集中させることで、家業の維持や先祖の祭祀を確実に次世代へ繋ぐことを重視したのです。
2| 家督相続はなぜ廃止されたのか? ~現代の相続への転換~

第二次世界大戦後、日本は大きな変革期を迎えました。日本国憲法が制定され、「個人の尊厳」や「法の下の平等」という基本的人権の尊重が最も重要な価値観となりました。
この新しい価値観に照らし合わせたとき、家督相続制度は以下のような問題点を持つと判断されました。
-
個人の権利の侵害
長男以外の相続人が財産を相続できないのは、個人の財産権や平等を著しく侵害するものでした。 -
女性の地位の低さ
男子が優先され、女性が戸主となる場合も制限があるなど、男女不平等を助長する側面がありました。 -
家族関係の不和
財産の独占は、兄弟姉妹間や配偶者との間で、深刻な「争族」の原因となることが多々ありました。
こうした理由から、1947年(昭和22年)に民法が改正され、家督相続制度は廃止されました。そして、現在私たちが採用している、「死亡による遺産相続制度(諸子均分相続制)」へと移行したのです。
3| 家督相続と現代の相続(法定相続)の主な違い
4| 現代でも家督相続が関係するケースと対処法

家督相続制度は廃止されましたが、以下のケースでは、現代の相続手続きにおいて家督相続の知識が必要となることがあります。
1.何代も前の相続登記がなされていない不動産
これが最も典型的なケースです。例えば、明治時代や大正時代、あるいは戦後の民法改正直後(1947年末まで)に亡くなった方が所有していた土地や建物で、相続登記がなされないまま何代も放置されている場合があります。
この場合、現在の所有者を明確にするためには、登記簿上の名義人から順に、過去の相続手続きを遡って行う必要があります。その際、旧民法が適用されていた時代の相続については、家督相続のルールに基づいて相続人を確定し、登記を行うことになります。
この家督相続の存在は、現代に生きる私たちにとって、時に思わぬ形で影響を及ぼします。特に、亡くなった方の調査を進める際、「あれ、こんなはずでは?」と困惑するケースが、本当に多くみられます。
なぜなら、現行の民法とは相続の基本的な考え方が全く異なるため、例えば「長男が当然すべてを相続する」という旧法下の認識と、現行法で定められた「すべての相続人に平等な権利がある」という原則との間に大きな乖離が生じるからです。これにより、誰が本当の相続人なのか、誰が財産を承継するのかが、現代の常識とは全く異なる結果になることも珍しくありません。
この「ズレ」が、古い時代の相続登記が放置された不動産などで、現代の私たちに複雑な問題として現れてくるのです。
~対処法~
このようなケースでは、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を遡って取得し、戸主やその時代の家族関係、家督相続人が誰であったかを特定する必要があります。非常に複雑な手続きとなるため、司法書士や行政書士といった専門家に相談することが不可欠です。
2.「家は長男が継ぐもの」という慣習が残る場合
現代の民法では、長男だけが遺産を単独で相続するという家督相続の考え方は存在しません。すべての相続人に法定相続分が保障されています。しかし、特に地方や古い家柄では、「長男がすべてを継ぐべきだ」という旧来の習慣や考え方が根強く残っている場合があります。
これにより、遺産分割協議の際に「長男が全部相続するべきだ!」と主張し、他の相続人が正当な権利を主張しにくい状況が生まれることがあります。
~対処法~
〇現行法の説明
まずは、相手に対して、現在の民法では「諸子均分相続」が原則であり、家督相続は廃止されていることを冷静に説明しましょう。
〇遺産分割協議
相続人全員で話し合いを行い、合意の上で遺産の分割方法を決定する「遺産分割協議」を行う必要があります。もし、全員が同意すれば、結果的に長男がすべての財産を相続することも可能ですが、他の相続人の同意が不可欠です。
〇遺留分への配慮
たとえ遺言書で「長男に全財産を相続させる」と書かれていたとしても、他の相続人には「遺留分」という最低限の相続分が保障されています。遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。
〇専門家への相談
話し合いが当事者同士でまとまらない場合は、弁護士に調停や審判の代理を依頼したりするなど、専門家のサポートを求めることが重要です。
5| まとめ ~古くて新しい「相続」の問題


家督相続は、現代では廃止された過去の制度ですが、日本の家族や財産の歴史に深く根ざしたものであり、今もなお、特に不動産や家族間の価値観に影響を与え続けています。
「家を継ぐ」という意識は、形を変えながらも現代に受け継がれていますが、現行の民法では、個人の権利が尊重され、相続人全員が財産を相続する権利を持っています。
もし、ご自身の相続に「家督相続」が関係しているかもしれないと感じた場合や、家族間で昔ながらの考え方による相続トラブルが発生しそうな場合は、一人で抱え込まずに、早めに行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に相談することが、スムーズな解決への第一歩となります。
このコラムが、日本の相続の歴史と現代の制度の橋渡しとなり、皆さんの相続に関する疑問解消の一助となれば幸いです。
当職は旧民法からの調査などもお取り扱いしております。ご状況にあわせて弁護士、司法書士にご紹介も可能です。ご不安な方はまず下記よりお問い合わせください。

執筆者
行政書士おちあい事務所 行政書士 落合真美
遺言や相続、建設業や産廃業などの許可申請でサポートを提供。人に、会社に、寄り添うことを大切にしています。



