
こんにちは。行政書士の落合です。
前回のコラム(参照)では、そもそも「家族信託」とは何か、その全体像について解説しました。ご自身の財産を家族に託すことで、将来の様々な不安に備えられる、とても柔軟な仕組みだということをご理解いただけたかと思います。
今回は、その家族信託がどのようなご家族に向いているのか、そして逆に、向いていないのはどんなケースなのかを、具体的な事例を交えながら詳しく解説してまいります。最近注目の家族信託。ご自身の状況に本当に家族信託が必要なのか、判断する上でのヒントになれば幸いです。
目次
1| 家族信託とは何か?
2| 家族信託に向いているケース
2-1 認知症への備えをしたい場合
2-2 共有名義の不動産がある場合
2-3 二次相続以降の財産の承継先を決めたい場合
2-4 障がいのある子や配偶者がいる場合
2-5 事業承継をスムーズに行いたい場合
3| 家族信託に向いていないケース
3-1 信託財産が少ない場合
3-2 家族関係が複雑・不仲な場合
3-3 受託者に適任者がいない場合
3-4 財産管理の目的が不明確な場合
5| まとめ
1| 家族信託とは何か?

家族信託とは、特定の目的(例えば、自分の老後の生活費や、障がいのある子の将来の生活など)のために、大切な財産(不動産や預貯金など)を信頼できる家族に託し、その管理や運用、そして処分を任せる仕組みです。財産を託す人を「委託者」、財産を託される家族を「受託者」、そして財産から得られる利益を受け取る人を「受益者」と呼びます。
家族信託の大きな特徴は、財産管理の柔軟性と、財産を複数世代にわたって承継できる点です。一般的な遺言や成年後見制度ではできないような、柔軟でオーダーメイドな財産管理を実現できます。
しかし、すべてのケースに家族信託が向いているわけではありません。制度の仕組みを理解し、ご自身の状況に本当に合っているのかを慎重に判断することが大切です。
2| 家族信託に向いているケース
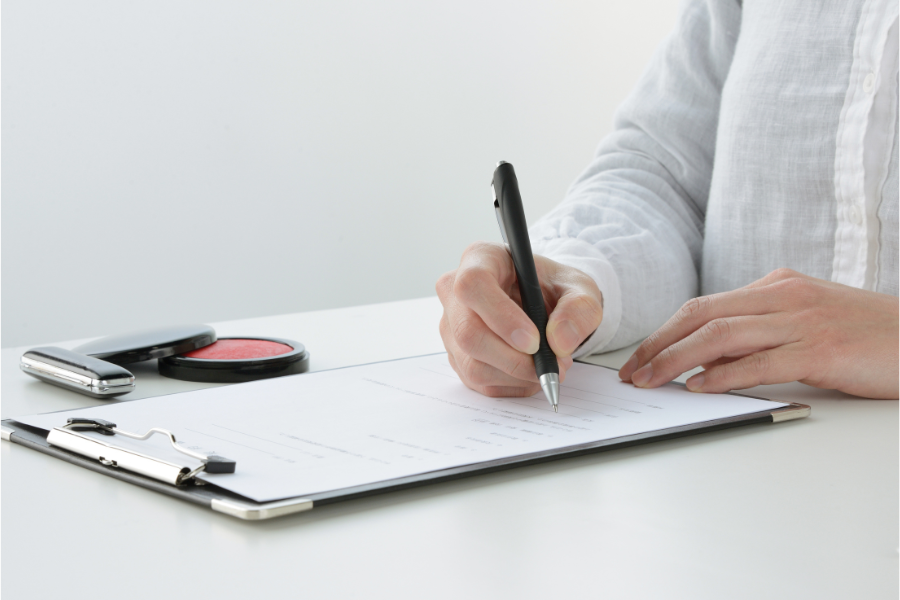
家族信託が特に有効なのは、以下のようなケースです。
2-1 認知症への備えをしたい場合
認知症になってしまうと、本人の意思能力がないと判断され、預金の引き出しや不動産の売買といった財産管理ができなくなります。成年後見制度を利用する方法もありますが、手続きが複雑で費用もかかり、後見人が家族の意図しない管理を行うリスクもあります。
家族信託であれば、委託者(財産の持ち主)が元気なうちに、受託者(財産を管理する家族)に財産を託しておくことができます。万一、委託者が認知症になったとしても、受託者が信託契約に基づき、財産をスムーズに管理・運用できるため、生活費に困ったり、不動産を売却できなくなったりする心配がありません。
2-2 共有名義の不動産がある場合
兄弟姉妹で共有している不動産がある場合、そのうちの一人が亡くなると、相続が複雑になります。さらに、相続した人が認知症になると、他の共有者の同意がなければ不動産を売却することも、有効活用することもできなくなってしまいます。
家族信託を利用すれば、共有名義の不動産を信託財産とし、信頼できる家族を受託者とすることで、不動産の管理を一元化できます。たとえ共有者の一人が認知症になったとしても、受託者がスムーズに不動産の管理や売却を進めることができ、将来的なトラブルを未然に防げます。
2-3 二次相続以降の財産の承継先を決めたい場合
一般的な遺言では、財産の行き先は一次相続(配偶者や子など)までしか指定できません。しかし、「自分が亡くなった後、妻が亡くなったら、その財産は長男ではなく、孫に渡したい」といった二次相続以降の承継先を決めたい場合があります。
家族信託であれば、信託契約書に二次、三次相続以降の財産の承継先を細かく指定できます。これにより、あなたの意思を確実に、複数世代にわたって実現させることが可能です。
2-4 障がいのある子や配偶者がいる場合
障がいのある子がいる場合、親が亡くなった後の生活が心配になるでしょう。遺言で財産を残すことはできますが、その子が財産を自分で管理できるかどうか、不安が残ります。
家族信託を活用すれば、親が元気なうちに、信頼できる親族を受託者とし、障がいのある子の生活費や医療費のために、計画的に財産を管理・運用させることができます。これにより、親が亡くなった後も、子が安心して生活を送れる環境を整えることができます。
2-5 事業承継をスムーズに行いたい場合
中小企業の経営者が高齢になり、事業を後継者に引き継ぎたいと考えている場合、家族信託は非常に有効な手段となります。株式を信託財産とすることで、議決権を後継者である受託者に集中させ、経営権を円滑に承継させることができます。これにより、相続による事業の混乱を防ぎ、安定した経営を維持できます。
3| 家族信託に向いていないケース

3-1 信託財産が少ない場合
家族信託は、公正証書の作成や専門家への相談費用など、初期費用がかかります。また、不動産の登記費用や登録免許税なども必要です。信託する財産が少ない場合、これらの費用が信託のメリットを上回ってしまう可能性があります。
3-2 家族関係が複雑・不仲な場合
家族信託は、信頼できる家族を受託者とすることが大前提です。受託者が財産を適切に管理・運用するためには、受益者や他の親族との間で、透明性の高いコミュニケーションが不可欠です。もし家族間で不仲であったり、財産をめぐる争いがある場合、家族信託が新たな火種となるリスクがあります。
3-3 受託者に適任者がいない場合
家族信託を成立させるためには、財産を管理する受託者が必要です。受託者は、財産の管理・運用だけでなく、税務申告や受益者への報告義務など、様々な責任を負います。もし、受託者になる適任者(信頼できる家族)がいない場合、家族信託の仕組み自体が成り立ちません。
3-4 財産管理の目的が不明確な場合
家族信託は、特定の目的のために財産を託すものです。目的が不明確なまま契約を結んでしまうと、受託者が財産をどう管理すればよいか分からず、トラブルの原因となる可能性があります。家族信託を検討する前に、なぜ家族信託をしたいのか、その目的を明確にすることが重要です。
4| 家族信託を検討する上での注意点

5| まとめ

家族信託は、柔軟で強力な財産管理・承継の手段です。特に、認知症対策、共有不動産の管理、二次相続以降の承継、障がいのある家族の生活支援、事業承継といったケースでその真価を発揮します。
しかし、初期費用や家族関係、そして受託者の適任者探しなど、検討すべき点は多岐にわたります。ご自身の状況を客観的に見つめ直し、専門家と相談しながら、最適な方法を選ぶことが、あなたの未来と大切な家族を守る最善の方法となるでしょう。
いかがでしたでしょうか。少しでも「家族信託についてもっと詳しく知りたい」「うちの家族の場合、どうなるの?」と感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。

執筆者
行政書士おちあい事務所 行政書士 落合真美
遺言や相続、建設業や産廃業などの許可申請でサポートを提供。人に、会社に、寄り添うことを大切にしています。



