
こんにちは。行政書士の落合です。
フリマアプリやネットオークションが私たちの生活に浸透し、不要になった洋服や読み終わった本、使わなくなった家電などを手軽に売買できる時代になりました。スマホ一つで誰でも簡単に「売る側」になれる今、多くの人が抱く疑問があります。「これって、商売になるの?」「何か特別な許可っているの?」と。
実は、個人が趣味の延長で中古品の売買を繰り返したり、副業として利益目的で中古品を扱ったりする場合、知らず知らずのうちに「無許可営業」となっている可能性があるのです。警察庁のデータによると、無許可営業による摘発も実際に発生しています。
そこで今回は、現代のビジネスシーンにおいて避けては通れない「古物商許可」について、その基本から取得のポイント、そして行政書士のサポートまで、わかりやすく解説していきます。
目次
1| 古物商許可って、そもそも何?
・ 「業として」って、具体的にどういうこと?
【古物商許可が必要なケースの例】
【古物商許可が不要なケースの例】
3| 古物商許可を取得するメリット
1.信頼性が向上する
2.仕入れルートが広がる
3.法的な安心感
4.銀行融資が受けやすくなる可能性
4| 古物商許可取得までの道のり ~難しさと行政書士のサポート~
1.要件の確認
2.申請書類の準備
3.警察署での申請と審査
6| まとめ ~古物商許可は「安心」と「信頼」を売るためのパスポート~
1| 古物商許可ってそもそも何?


「古物商許可」とは、中古品(古物)を「業として」、つまり反復・継続して売買したり、交換したり、あるいは貸し借りする際に必要となる許可のことです。この許可は、警察署が窓口となり、管轄の公安委員会から与えられます。
なぜこんな許可が必要なのでしょうか? その背景には、盗品が市場に流通するのを防ぎ、犯罪の捜査に役立てるという目的があります。古物商には、取引相手の確認や、取引内容の記録・保管といった義務が課せられており、これにより不法な品の流通を食い止めているのです。
「業として」って、具体的にどういうこと?
ここが一番のポイントです。「業として」というのは、「利益を得る目的で、反復・継続的に行う」ことを指します。つまり、以下の場合は古物商許可が必要です。
- 仕入れて売る
中古品を買い取って販売する(リサイクルショップなど) - 交換する
中古品と中古品を交換する - レンタルする
中古品を貸し出す(レンタルDVD店など) - 委託を受けて売る
他人から中古品を預かって販売し、手数料を得る
では、具体的にどんなケースで許可が必要になるのでしょうか?
【古物商許可が必要なケースの例】
・リサイクルショップの経営
店舗を構えて中古品を売買する。
・ネットオークション・フリマアプリでの転売
利益目的で中古品を安く仕入れて、繰り返しネット上で販売する。
・中古自動車販売・買取
中古車を仕入れて販売する。
・中古ブランド品販売
中古のバッグや時計などを仕入れて販売する。
・古本屋・中古CD/DVD店
中古の書籍やソフトを販売する。
・金券ショップ
商品券やチケットなどを売買する。
・スクラップ業者
中古の金属などを買い取り、加工して販売する。
・中古農機具の売買
農業機械を仕入れて販売する。
【古物商許可が不要なケースの例】
・自分の不要品を売る
一度きり、またはごくたまに、自宅の使わなくなった物をフリマアプリで売る場合。
・海外から輸入した新品を売る
中古用の新品であれば古物には該当しません。
・自分で製造・製作したものを売る
ハンドメイド品など。ただし、材料が中古品の場合は注意が必要です。
・無償で引き取ったものを売る
ボランティアなどで無償で譲り受けたものを販売する場合。
ただし、対価を得ているとみなされる場合は必要になることもあります。
「利益目的」「反復継続」がキーワードです。少しでも「あれ?」と感じたら、専門家への相談を検討することをおすすめします。
2| 無許可で営業するとどうなる?恐ろしい罰則

3| 古物商許可を取得するメリット

面倒な手続きをクリアしてまで許可を取得することには、様々なメリットがあります。
1.信頼性が向上する
古物商許可証は、警察の厳しい審査をクリアした事業者にのみ与えられるものです。これにより、顧客や取引先からの信頼が得られ、安心して取引ができるようになります。
2.仕入れルートが広がる
古物市場への参加や、一般の方からの買取など、許可がなければ利用できない正規の仕入れルートを活用できるようになります。これにより、商品の品揃えを増やし、事業を拡大するチャンスが広がります。
3.法的な安心感
無許可営業の摘発リスクから解放され、安心して事業に専念できます。
4.銀行融資などが受けやすくなる可能性
許可事業として認められることで、金融機関からの融資や補助金の申請など、事業展開の選択肢が広がる場合があります。
4| 古物商許可までの道のり ~難しさと行政書士のサポート~
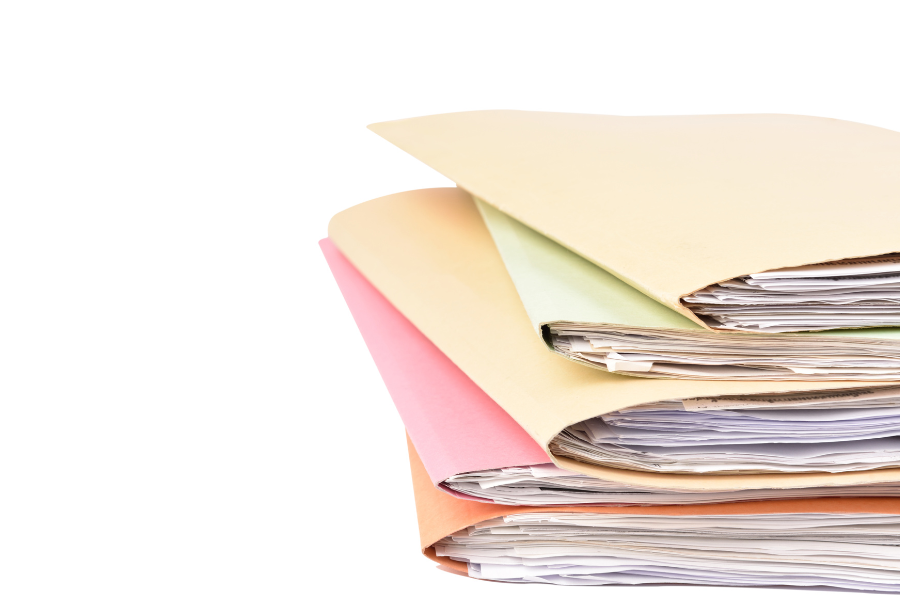
古物商許可の取得は、決して簡単な道のりではありません。主な取得要件と手続きの複雑さを知っておきましょう。
1. 取得要件の確認
以下のいずれかに該当する人は、原則として許可を取得できません(欠格要件)。
- 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない人
- 破産手続き開始の決定を受け、復権を得ていない人
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人
- 住居が定まらない人
- 精神機能の障害により、古物営業を適正に行うことができない人
これら以外にも、未成年者の場合は保護者の同意や、営業所の準備、営業管理者の選任など、細かな要件があります。
2. 申請書類の準備
申請には非常に多くの書類が必要です。
- 古物商許可申請書
- 住民票の写し(本籍地記載のもの)
- 身分証明書(本籍地の役所で発行される、破産者でないことなどを証明する書類)
- 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類)
- 登記事項証明書(法人申請の場合)
- 賃貸借契約書のコピー(営業所が賃貸の場合)
- 営業所の見取り図・略図
- URLを届け出る場合は、使用権限を疎明する資料
- その他、必要に応じて追加書類
これらの書類は、本籍地の役所や法務局、賃貸人など、様々な場所から集める必要があり、非常に手間と時間がかかります。
3. 警察署での申請と審査
必要書類が揃ったら、管轄の警察署の生活安全課(または防犯課)に申請します。書類に不備があれば受理されず、何度も足を運ぶことになりかねません。申請後、通常は40日程度の審査期間を経て、問題がなければ許可が下ります。この間、警察官による営業所の立ち入り検査や、申請内容に関する質問が行われることもあります。
5| 行政書士の役割 ~複雑な手続きをスムーズに~

これだけ多くの書類と複雑な手続きがある古物商許可申請を、すべて自分で対応するのは、特に本業がある方にとっては大きな負担です。そこで頼りになるのが、私たち行政書士です。
行政書士は、これらの申請書類の作成を代行し、必要書類の収集についてもアドバイスやサポートを行うことができます。
- 必要書類の特定と収集支援
複雑な要件に合わせた書類を漏れなく特定し、スムーズな収集をサポートします。 - 正確な書類作成
専門知識に基づき、警察が求める形式に沿った申請書や添付書類を正確に作成します。 - 警察署との連携
事前の相談から申請、審査中の質疑応答まで、警察署とのやり取りを円滑に進めるサポートも可能です。 - 時間と手間の削減
お客様は本業に集中しながら、古物商許可の取得を進めることができます。 - 無許可営業のリスク回避
確実に許可を取得することで、知らずに法律違反をしてしまうリスクを回避できます。
6| まとめ ~古物商許可は「安心」と「信頼」を売るためのパスポート~

フリマアプリなどで手軽に中古品を売買できる時代だからこそ、古物商許可の重要性は増しています。「知らなかった」では済まされない厳しい罰則がある一方で、許可を取得すれば、ビジネスの信頼性が高まり、新たなチャンスが広がります。
個人で中古品販売を始めたい方、副業として考えている方、そしてすでに事業を営んでいる方も、「これって古物商許可っているのかな?」と少しでも疑問に思ったら、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。
私たちは、あなたのビジネスが法的に安心して行えるよう、そしてあなたの「売る」という挑戦が成功するよう、全力でサポートいたします。古物商許可は、単なる手続きではなく、あなたのビジネスを「安心」と「信頼」で彩るための大切なパスポートとなるでしょう。
いかがでしたでしょうか。古物商許可の取得を検討されている方や、既に事業をされている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。もし、さらなる疑問や具体的なご相談があれば、いつでもお気軽にお声がけください。

執筆者
行政書士おちあい事務所 行政書士 落合真美
遺言や相続、建設業や産廃業などの許可申請でサポートを提供。人に、会社に、寄り添うことを大切にしています。



