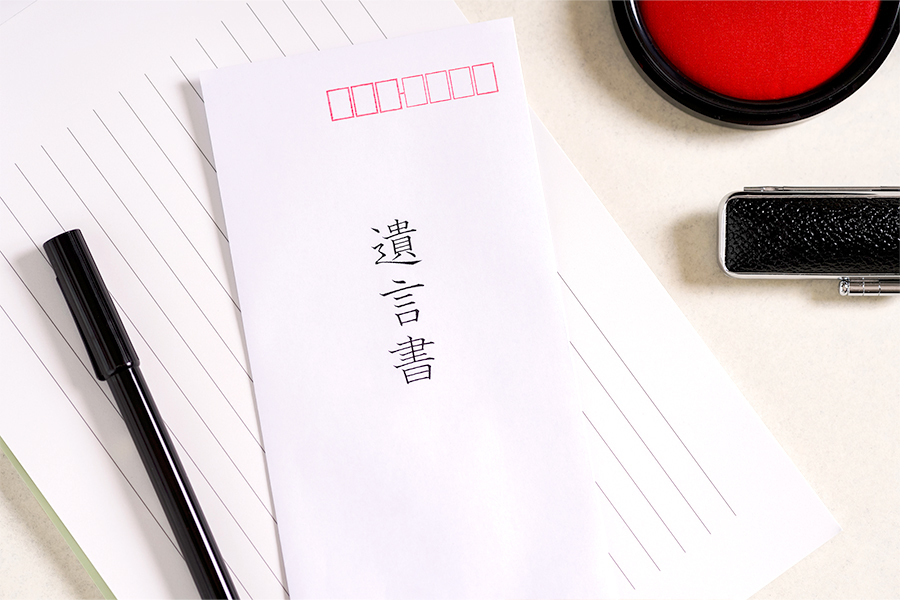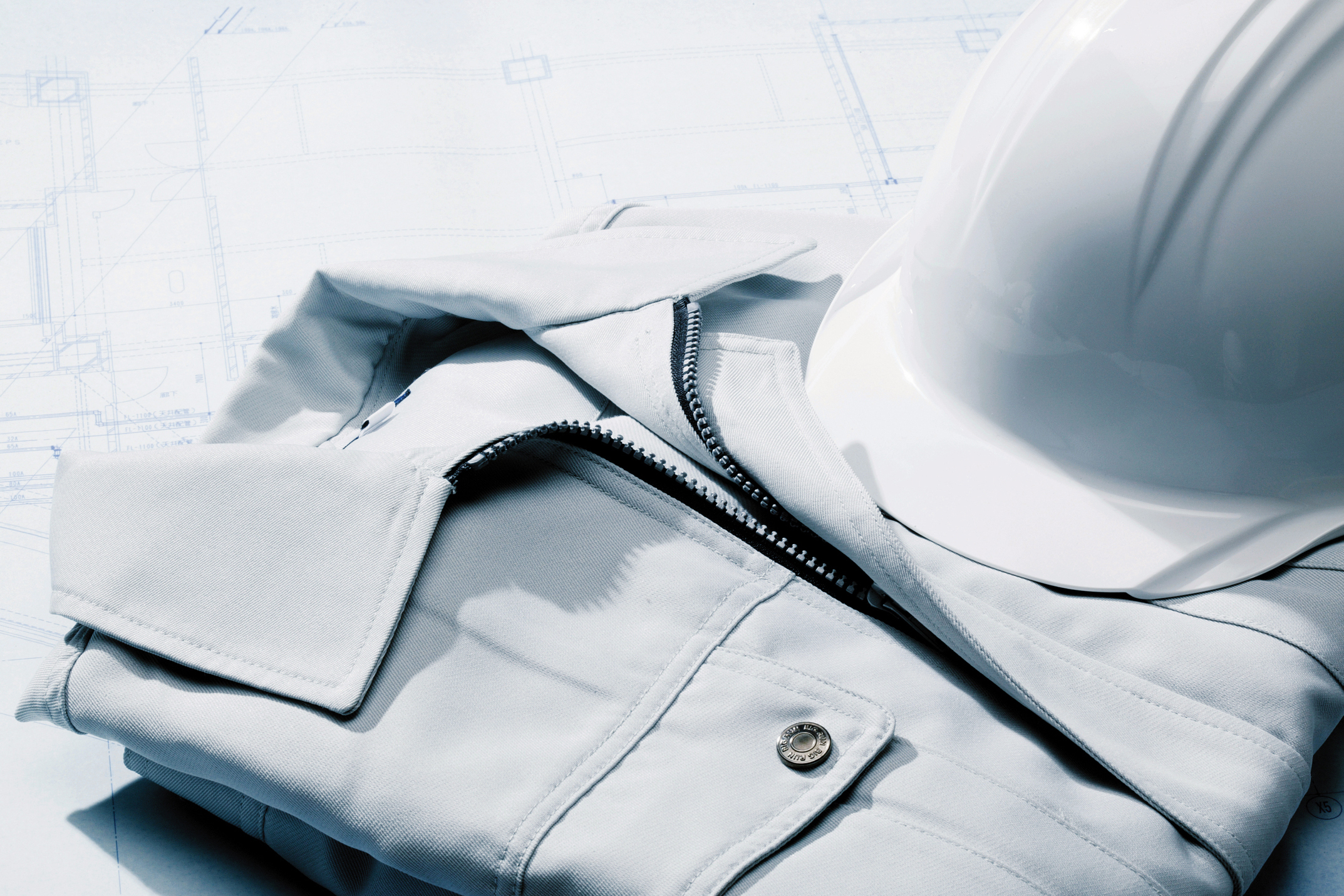こんにちは。行政書士の落合です。
これまで当事務所のコラムでは、「空き家等管理活用支援法人」や「特定居住支援法人」といった、主に「家屋(建物)」や「居住支援」に焦点を当てた制度をご紹介してきました。空き家問題を解決するための法整備が進む中で、これらの法人が果たす役割は非常に大きなものです。
しかし、私が過去から現在まで携わってきた経験から、一つの大きな真理に突き当たります。それは、「家屋は、土地という基盤があって初めて存在している」という事実です。
建物の活用や解体を検討しても、その土台である土地の所有者が分からなければ、対策は途端に足止めを食らってしまいます。「建物はどうにかできそうなのに、土地の権利が壁になって動かせない」……。こうしたジレンマを打破するために誕生したのが、令和4年の法改正で新設された「所有者不明土地円滑化等促進法人(以下、促進法人)」です。
今回は、国がこの制度を創設した真の狙いと、その指定申請を目指す法人様へ向けて、当事務所ができるサポートについて詳しくお話しします。